言語の壁を越える安否確認:システムにおける英語表記の重要性とその影響
2025/04/23.

災害大国・日本において、企業や自治体が従業員や住民の安全を守るために欠かせないのが安否確認システムです。しかし近年、グローバル化が進み外国人従業員や住民が増える中、言語の壁や操作の難しさから災害発生時に適切な安否確認ができないケースが少なくありません。そのため、英語をはじめとするシステムの多言語対応への需要が高まっています。
本コラムでは安否確認システムの基本から、多言語対応システムの導入ポイント、最新技術を活用した未来の安否確認システムまで、幅広く解説します。企業や自治体がどのように多文化共生を実現しながら、災害時の安全確保を強化できるのか――そのヒントをぜひ見つけてください。
index
安否確認システムの重要性と外国語対応の必要性
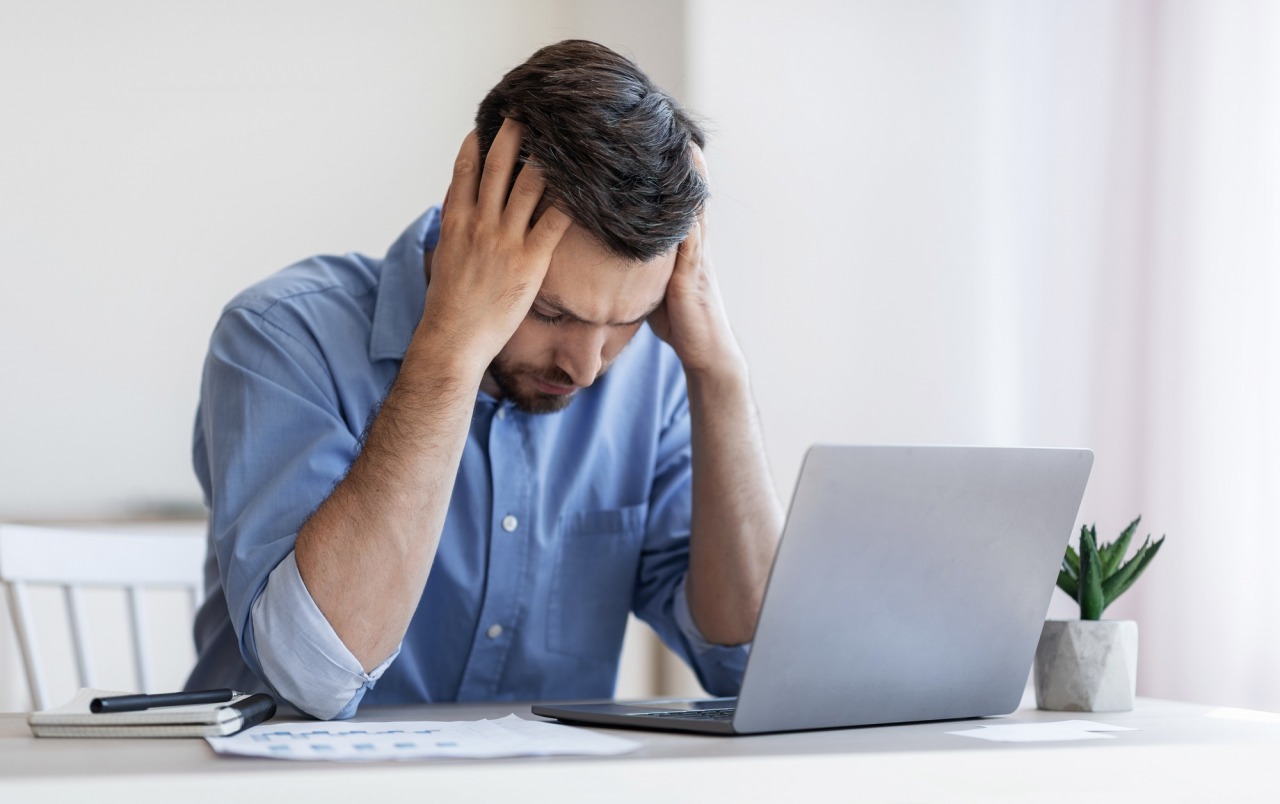
災害時に求められる「すぐに、確実に」安否を確認できる仕組み
日本は地震や台風、大雨、津波など、自然災害が多い国です。企業や自治体では、これらの災害に備え、従業員や住民の安全を守るための「安否確認システム」を導入することが一般的になっています。安否確認システムとは、災害時に従業員や関係者の安否を迅速に確認し、必要な支援や対応を行うためのサービスです。
従来の安否確認は、電話やメール、グループチャットを使って連絡を取ることが主流でした。しかし、大規模な災害時には電話回線がパンクしたり、個々に連絡を取る手間がかかったりして、すぐに状況を把握できないケースも多々ありました。そこで、多くの企業が「安否確認システム」を導入し、一斉送信による効率的な連絡や、自動集計機能による迅速な対応を可能にしています。
しかし、グローバル化が進む現代において、日本語だけの安否確認システムでは、十分な対応ができないケースが増えてきています。特に外国人従業員や海外拠点の社員が多い企業では、「多言語対応が不可欠」な状況になりつつあるのです。
企業における外国語対応の必要性
近年、多くの企業では、海外からの技術者やエンジニア、研究者、専門職などの採用が増加しています。日本語の通知のみが送られる安否確認システムでは、外国人従業員は内容を理解できず適切に返信できない場合があり、企業側もすべての安否の把握ができず必要な対応が遅れることに繋がる可能性があります。つまり、災害時には「迅速な情報伝達」が命を守るカギとなるため、言語の壁を取り払うことが極めて重要です。
さらに海外拠点を持つ企業では、日本の災害が現地にも影響を及ぼすことがあります。例えば日本の本社が大規模な地震の影響で業務がストップすれば、海外の支社や取引先にも影響が及びます。日本の状況を正確に伝え、適切な対応を促すためにも、英語などの多言語での情報提供が必要になるのです。
災害時に多言語対応がないと何が起こるのか?
では安否確認システムが日本語しか対応していなかった場合、具体的にはどのようなリスクがあるのか、さらに踏み込んで考えてみましょう。
- 外国人従業員が通知の意味を理解できず、適切に返信できない。
結果として、企業は全社員の状況を正しく把握できず、必要な支援を迅速に行えない。 - 災害時の指示や避難情報が伝わらない。
例えば、「〇〇地域は避難指示が出ています」「〇〇に集合してください」といった指示を外国人従業員が理解できないと、適切に避難できず、命の危険にさらされる可能性がある。 - 海外拠点や外国人取引先との連携がうまくいかない。
日本の本社が緊急事態に陥った際、海外拠点に状況を正確に伝えられず、事業継続に支障をきたすことがある。
こうしたリスクを防ぐためにも、安否確認システムの多言語対応が必要不可欠なのです。
多言語対応の安否確認システムで企業の防災力を向上
多言語対応の安否確認システムを導入することで、以下のようなメリットがあります。
- 外国人従業員が迅速に状況を把握し、適切に対応できる。
- 企業が正確な安否情報を把握し、適切な支援を行える。
- 災害時の混乱を最小限に抑え、業務継続の支障を減らせる。
このメリットは特に、観光業や製造業など、さまざまな国の人々が関わる業界において大きな強みとなるでしょう。
ここまで安否確認システムの概要と、なぜ多言語対応が必要なのかということを解説してきました。
次章では、多言語対応の安否確認システムを導入する際のポイントについて詳しく解説します。
多言語対応の安否確認システム導入のポイント

前章では、災害時の安否確認システムに多言語対応が求められる理由について解説しました。
では、安否確認システムを導入するときは具体的にどのようなポイントを押さえてシステムを選ぶべきなのでしょうか?本章では、多言語対応の安否確認システムを導入する際に重視すべきポイントを詳しく解説します。
1.多言語での通知・返信機能があるか
最も基本的でありながら、最も重要なのが「通知と返信が多言語で可能かどうか」です。
例えば、以下のような機能があると理想的です。
- 通知を送信する際に言語を自動翻訳できる。
- 受信者が自分の言語を選択できる。
- 安否報告を母国語で返信できる。(システム側で翻訳される)
一例として、日本語で「地震が発生しました。無事ですか?」という通知を送信すると、英語圏の従業員には「An earthquake has occurred. Are you safe?」というメッセージが届くような仕組みがあると、スムーズな情報伝達が可能になります。
また、「返信の多言語対応」も重要なポイントです。外国人従業員に日本語での返信を求めると、内容の理解に時間がかかり適切な安否報告ができない可能性があります。そのため、「無事」「けがをした」「避難中」などの選択肢を、それぞれの母国語で表示できる仕組みがあると、より安心して利用できるでしょう。
2.操作がシンプルで直感的に使えるか
多言語対応のシステムであっても、操作が複雑だと実際の災害時にうまく機能しません。特に、外国人従業員が初めて使うシステムである場合、できるだけシンプルで直感的な操作が求められます。操作性、つまりUIについては日本人従業員にとっても同様に重要なポイントとなります。
例えば、以下のような設計があると便利です。
- ボタンやアイコンを活用し、視覚的に分かりやすいインターフェースになっている。
- 簡単なタップやクリックで安否報告が可能である。
- 文字入力が不要な選択式の回答形式である。
緊急時には冷静に対応することが難しいため、できるだけ手間なく安否確認ができるシステムを選ぶことが大切です。
3.多様な通信手段に対応しているか
災害時は、通常の通信手段が使えなくなることもあります。そのため、安否確認システムがメール/SMS/専用アプリ/電話など、複数の通信手段に対応しているかを確認することも重要なポイントのひとつです。
例えば、以下のような方法があると、より確実に安否を確認できます。
- メール通知(PC・スマホの両方で受信可能)
- SMS通知(携帯電話の通信が混雑していても受信しやすい)
- 専用アプリのプッシュ通知(より詳細な情報を提供可能)
- 音声通話による自動応答(インターネットが使えない場合の対策)
特に、外国人従業員の場合、日本の携帯電話を持っていないこともあるため、SMSや海外の電話番号にも対応しているシステムを選ぶと安心です。
4.企業のニーズに応じたカスタマイズが可能か
企業によって、安否確認システムに求める要件は異なります。多言語対応だけでなく、企業ごとのニーズに応じたカスタマイズが可能かどうかも重要なポイントです。
例えば、以下のようなカスタマイズ機能があると便利です。
- 部署や拠点ごとに異なる言語で通知を送信できる。
- 特定の従業員には英語、それ以外は日本語で通知する設定ができる。
- 企業独自の質問項目を追加できる。(例:「自宅待機が可能か?」など)
カスタマイズのためのコストがかかる場合がありますが、従業員構成や業務内容に合わせて柔軟にカスタマイズできるシステムを選ぶことで、より実用的な運用が可能になるでしょう。
5.システム導入後のサポートが充実しているか
安否確認システムを導入した後、従業員がしっかり使いこなせるようにするためには、導入後のサポート体制も重要です。特に、多言語対応の場合、外国人従業員向けのトレーニングやマニュアルが整備されているかどうかもチェックポイントになります。
以下のようなサポートがあると安心でしょう。
- 多言語対応の操作マニュアルやFAQが用意されている。
- 外国人従業員向けの研修や説明会が実施できる。
- 導入後もサポートデスクが多言語対応している。
いざという時にシステムが使えなければ意味がないため、導入前に従業員向けのトレーニングを行い、操作に慣れておくことが大切です。
多言語対応の安否確認システムで従業員の安全を守る
多言語対応の安否確認システムを導入することで、企業は災害時の情報伝達をスムーズにし、外国人従業員の安全を守ることができます。
システムを選ぶ際は、多言語での通知・返信機能、操作のしやすさ、多様な通信手段の対応、企業ニーズに応じたカスタマイズ、導入後のサポート体制などを考慮することが重要です。
次章では、災害時に求められる多文化共生と安否確認の仕組みについて見ていきます。
災害時に求められる多文化共生と安否確認の仕組み

2025年時点で、日本に住む外国人の数は376万人を超え※1、企業や自治体にとっても外国人住民・従業員への対応が不可欠になっています。このような背景のもと、企業や自治体がどのように安否確認システムを活用し、外国人を含む多様な人々の安全を確保するのか、本章では災害時における多文化共生の視点と、安否確認システムが果たす役割について解説します。
※1:2025年3月14日 出入国在留管理庁発表
多文化共生を実現する安否確認システムの役割
安否確認システムは、企業や自治体が外国人従業員・住民の安全を確保するための強力なツールです。特に以下の点で、多文化共生を促進する重要な役割を果たします。
- 多言語対応による情報伝達の強化
災害時には迅速で正確な情報が求められます。
多くの安否確認システムでは、英語・中国語・スペイン語・ベトナム語など、複数の言語で通知を送信できる機能を備えており、この機能を活用すれば、企業や自治体は災害時でも迅速に正確な情報を伝え、外国人従業員や住民の安全を確保できます。 - シンプルな操作で誰でも簡単に安否確認が可能
外国人従業員や住民の中には、日本の防災システムに慣れていない人も多いため、直感的に操作できる安否確認システムを導入することが重要です。
例えば、次のような機能があると、言葉の壁を超えてスムーズな安否確認が可能になります。- ボタンを押すだけで「無事」「軽傷」「避難中」などを報告できる。
- ピクトグラム(絵記号)を用いたアイコンなどを活用した視覚的なインターフェースで、文字を読めなくても操作できる。
- 翻訳機能付きで、日本語が分からなくても自動で母国語に変換される。
- SNSやアプリを活用したリアルタイムな情報共有
近年では、安否確認システムと連携したSNSやアプリを活用し、リアルタイムで情報共有を行う企業や自治体が増えています。
例えば、- LINE、WhatsApp、WeChatなど、外国人に馴染みのあるツールを活用し、緊急通知を送る。
- GPS機能を活用し、従業員や住民の現在地を特定して適切な避難指示を出す。
- チャットボットを導入し、外国人が知りたい情報を自動で提供する。
このように、最新の技術を活用することで、より迅速で的確な安否確認が可能になり、外国人を含めた多様な従業員・住民の安全を確保できます。
企業や自治体が取るべき多文化共生の防災対策
安否確認システムを最大限に活用するためには、企業や自治体が平時から多文化共生の視点を持ち、防災対策を強化することが重要です。
具体的には、次のような取り組みが求められます。
- 多言語での防災マニュアルを作成し、外国人従業員や住民に配布する。
- 避難訓練を実施し、外国人が実際に参加できる環境を整える。
- 災害時に備えて、定期的にテストを行う。
- 災害発生時に、企業や自治体がどのように対応すべきかのルールを策定する。
このような準備をしておくことで、いざという時にスムーズに対応でき、多文化共生の環境を整えることができます。
多文化共生と安否確認の未来
外国人従業員や住民が増加する中、日本社会全体で「多文化共生の防災対策」を推進することが求められています。その中で、安否確認システムは単なる災害対策ツールではなく、「日本に暮らすすべての人々が安心して生活できる社会」を実現するための重要なインフラとなるでしょう。
今後は、より高度な翻訳技術やAIを活用し、よりスムーズな多言語対応を可能にする安否確認システムが登場することが期待されます。企業や自治体は、こうした最新技術を取り入れながら、外国人を含むすべての人々が安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいくことが重要です。
次章では、最新技術と今後の安否確認システムの展望について詳しく解説します。
最新技術と今後の安否確認システムの展望

これまでの章で、安否確認システムの重要性、多言語対応の必要性、そして多文化共生の視点からの活用方法について解説してきました。
近年、技術の進化によって、安否確認システムも大きく変わりつつあります。特に、AI(人工知能)、IoT(ネットでつながるスマート家電やスマート機器)、クラウド、ビッグデータ、モバイルアプリなどの最新技術を活用することで、より迅速で的確な安否確認が可能になっています。
本章では、これからの安否確認システムがどのように進化していくのか、今後の展望を詳しく見ていきます。
AI(人工知能)の活用による効率化と精度向上
AIの進化により、安否確認システムは単なるメッセージの送受信ツールから、よりインテリジェントな意思決定支援ツールへと変貌を遂げつつあります。
例えば、AIを活用した未来の安否確認システムには以下のような機能が考えられます。
- AIチャットボットによる自動応答機能
災害時に、従業員や住民がAIチャットボットと対話しながら、自分の状況を報告したり、避難情報を得たりすることが可能になるかもしれません。英語をはじめとする多言語対応のAIチャットボットを導入すれば、言葉の壁を超えたスムーズな情報共有が実現できるでしょう。 - 状況に応じた最適な避難指示を提供
AIが被災地のリアルタイムデータ(天候、地震の規模、交通情報など)を解析し、各従業員や住民に最適な避難ルートや行動指針を通知することができます。 - 安否データの自動分類・分析
企業や自治体が、従業員・住民の安否情報をリアルタイムで分析し、必要な支援がどこに必要なのかを迅速に判断するのに役立ちます。
IoTとウェアラブルデバイスを活用したリアルタイム安否確認
IoTやウェアラブルデバイスの進化により、災害時の安否確認の精度とスピードが向上します。従来の安否確認システムは、主に「スマートフォンを使った応答」が中心でしたが、IoT技術の導入により、より多様な方法で安否確認が可能になります。
- スマートウォッチやウェアラブルデバイスを活用
将来の安否確認システムでは、スマートウォッチやウェアラブルデバイスを装着することで、心拍数や位置情報をリアルタイムで送信し、本人が意識を失っている場合でも、自動で「異常状態」として検知・報告することが可能になるかもしれません。 - ビーコンやGPSを利用した位置情報の自動送信
建物内にビーコン(Bluetooth通信デバイス)を設置し、従業員や住民の現在位置をリアルタイムで把握するシステムが開発されています。GPSと組み合わせることで、「このエリアにいる人の安否を優先的に確認する」といった柔軟な対応が可能になるでしょう。 - 災害発生時に自動で安否確認を開始
地震や津波などの大規模災害が発生した際、IoTデバイスが震度や異常を検知し、自動で安否確認システムを起動する仕組みが開発されています。これにより、災害発生直後の混乱を最小限に抑えることができます。
弊社が提供している「安否コール」は、IoT機器に対応したクラウド型安否確認システムです。IoT機器との連携技術については、日本と米国で特許を取得しています。
クラウド型安否確認システムの普及とメリット
安否確認システムは、従来「社内サーバに設置されたオンプレミス型」が主流でしたが、近年はクラウド型の安否確認システムが普及しています。当社の「安否コール」もクラウド型安否確認システムです。
クラウドを活用することで、よりスムーズな運用が可能になります。
- どこからでもアクセス可能
クラウド型安否確認システムは、インターネット環境さえあればどこからでも利用できるため、海外拠点やリモートワークの従業員とも素早く連携できます。 - コストの削減
クラウド型のシステムは、サーバや保守管理のコストが不要なため、中小企業や自治体でも導入しやすいのが特徴です。 - リアルタイムなデータ共有
安否情報がリアルタイムでクラウド上に集約され、複数の関係者(企業、自治体、消防、警察など)が一元管理できる仕組みを作ることも可能になります。
多言語対応のさらなる進化
これまで多言語対応の安否確認システムについて触れてきましたが、今後はより高度な翻訳技術やAIを活用したリアルタイム対応が求められます。
- AI翻訳によるリアルタイムメッセージ変換
最新のAI翻訳技術を活用すれば、日本語で送信されたメッセージが即座に英語・中国語・スペイン語・ベトナム語などに自動翻訳されるシステムが一般化するでしょう。 - 音声対応の安否確認
文字だけでなく、音声での安否報告や情報受信が可能になれば、識字率が低い地域の外国人住民や高齢者にも利用しやすくなります。 - より多くの言語への対応
現在、多くの安否確認システムは主要な言語(英語・中国語など)のみ対応していますが、今後はより多くの言語に対応し、真のグローバル対応が進んでいくでしょう。
未来の安否確認システムとは?
最新技術の進化により、安否確認システムは今後ますます高度化・効率化していくことが予想されます。
- AIやIoTを活用したリアルタイム安否確認
- クラウド型サービスによる即時データ共有
- 翻訳技術の向上による多言語対応の強化
- 音声・ウェアラブルデバイスを活用した安否報告の多様化
企業や自治体がこうした最新技術を活用しながら、多文化共生に対応した安否確認システムを整備することで、誰もが安心して生活・働くことができる社会の実現が可能になるでしょう。

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。
- 事業内容
- デジタルマーケティング支援
デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格
- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)
プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))
ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)










